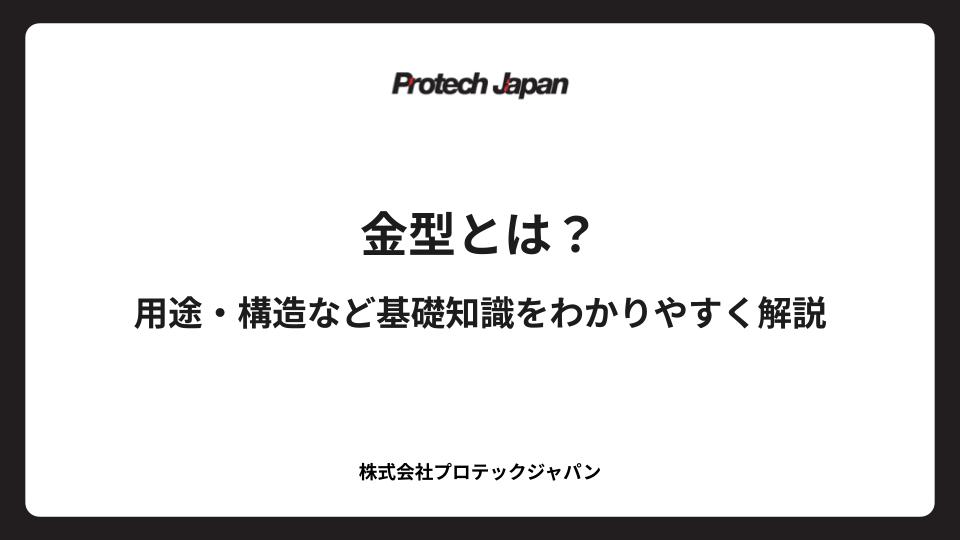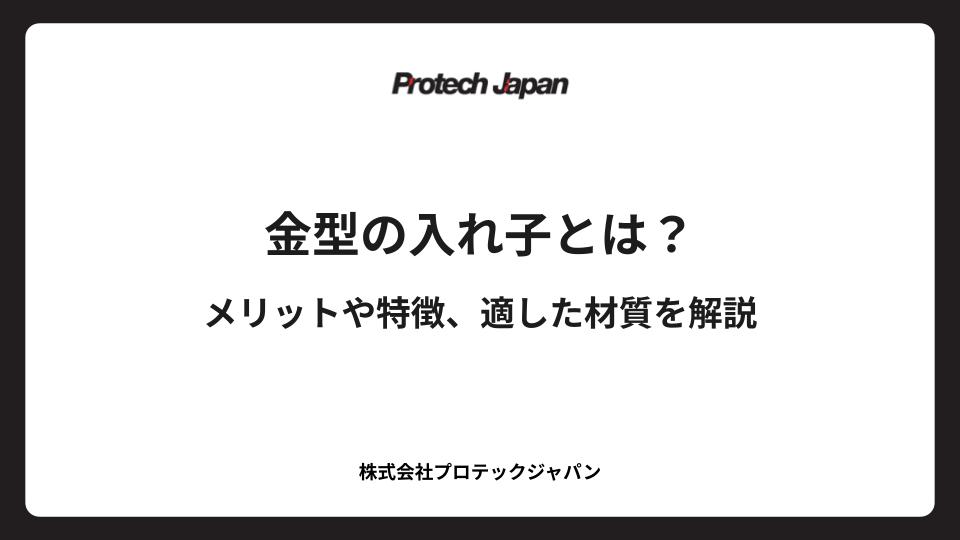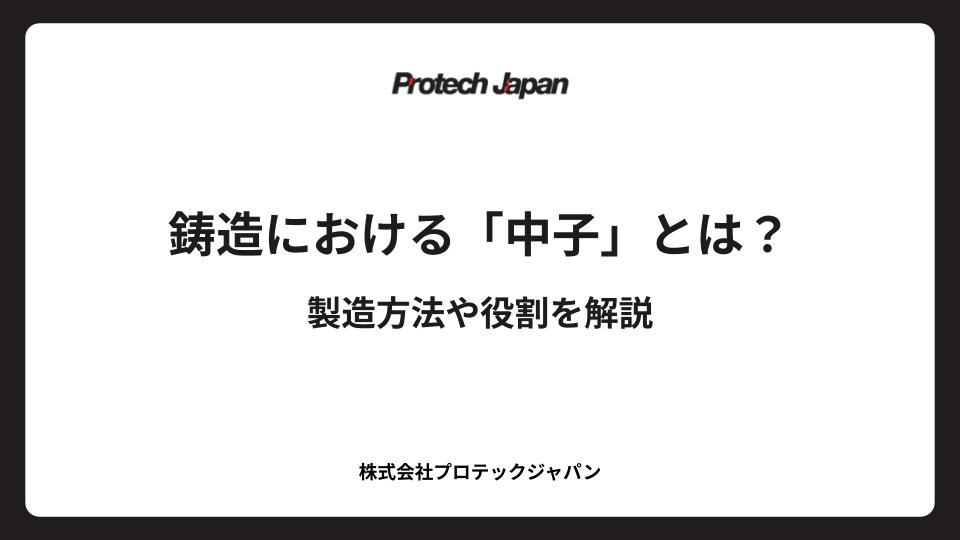製造業における試作品開発や小ロット生産において、真空注型は重要な製造手法の一つです。
金型製作のコストを抑えながら、高品質な樹脂製品を短納期で製造できる真空注型は、製品開発のスピードアップとコスト削減を両立させる有効な選択肢となっています。
本記事では、真空注型の基本的な仕組みから、メリット・デメリットまでわかりやすく解説します。
関連記事:真空注型とは?小ロット生産に最適でコスト削減と短納期を実現
真空注型とは
真空注型(しんくうちゅうけい)とは、主に製品の試作や小ロット生産に用いられる樹脂成形技術の一つです。
マスターモデル(原型)から作製したシリコーン型に、真空環境下で液状のウレタン樹脂などを注入し、硬化させて製品を複製します。
この製法は、射出成形のような金型製作に比べて初期費用を大幅に抑えられ、短期間での製品化が可能なため、開発期間の短縮やデザイン検証、機能試作に広く利用されています。
真空注型の仕組み・工程をわかりやすく解説
真空注型は、真空状態を利用して樹脂の気泡混入を防ぎながら精密な成形を行う点が特徴です。具体的には以下のような手順を踏んで行われます。
①マスターモデルの作成
まず、複製したい製品の元となる「マスターモデル」を作成します。このマスターモデルは、3Dプリンター(光造形や粉末焼結など)や切削加工によって製作されることが一般的です。
最終製品の寸法精度や表面品質はマスターモデルの精度に大きく依存するため、非常に重要な工程となります。
②シリコーン型の製作
次に、作成したマスターモデルを埋め込み、液状のシリコーン樹脂を流し込んで硬化させることで、マスターモデルの形状を転写した「シリコーン型」を作製します。
このシリコーン型は、通常、製品を取り出しやすいように複数のパーツに分割されます。シリコーンの柔軟性により、複雑な形状の製品でも型から容易に取り出すことが可能です。
③真空脱泡と注入
作製したシリコーン型を真空注型機内にセットし、液状のウレタン樹脂などの主剤と硬化剤を混合します。この混合過程で発生する気泡や、型に注入する際に巻き込まれる気泡を、真空ポンプで吸引することで徹底的に除去します。
気泡が除去された状態で型に樹脂を注入するため、気泡のない高精度な成形品を得ることができます。
④硬化・取り出し
樹脂が注入されたシリコーン型は、真空注型機内または専用のオーブンで一定時間加熱され、樹脂が完全に硬化するのを待ちます。
樹脂が硬化したら、シリコーン型から成形品を慎重に取り出します。取り出した製品は、必要に応じてバリ取りや研磨、塗装などの後処理が施され、最終的な製品として仕上げられます。
真空注型の4つのメリット
真空注型は、従来の金型を用いた製造と比較して、コストや納期、対応可能な形状の面で優れた特性を発揮します。ここでは、真空注型がもたらす主要な4つのメリットについて詳しく解説します。
①金型製作コストの大幅削減
真空注型の最大のメリットの一つは、金型製作にかかるコストを大幅に削減できる点です。射出成形などで用いられる金属製の金型は、高精度な加工が必要なため製作に多大な費用と時間がかかります。これに対し、真空注型では、マスターモデルを基に製作するシリコーン型を使用します。
シリコーン型は、金属金型に比べて材料費が安価であり、加工も容易なため、製作にかかるコストを格段に抑えることが可能です。これにより、初期投資を低く抑えられ、特に試作開発段階や少量生産において、経済的な負担を軽減できます。
②短納期での製品提供が可能
製品開発においてスピードは非常に重要です。真空注型は、短納期での製品提供を可能にする製造プロセスとして注目されています。
金属金型の製作には数週間から数ヶ月を要することが一般的ですが、シリコーン型であれば、マスターモデルが完成していれば数日から1週間程度で製作が可能です。
この型の製作期間の短縮により、製品開発サイクル全体の期間を大幅に短縮し、市場への投入を早めることができます。デザインの検証や機能評価のための試作品を迅速に手に入れたい場合に、真空注型は非常に有効な手段となります。
③小ロット生産に最適
多品種少量生産や限定品、試作品の製作において、真空注型は非常に優れた選択肢となります。金型製作コストが低いため、少量生産でも製品単価が高騰しにくく、経済的に合理的な生産が可能です。
例えば、新製品開発におけるデザイン確認用モデル、機能検証用のプロトタイプ、市場調査用の限定品、あるいは展示会用のサンプルなど、数個から数百個程度の生産が必要な場合に、真空注型はコストパフォーマンスに優れています。射出成形のような大量生産には向きませんが、特定のニーズに対して柔軟に対応できる点が強みです。
④複雑形状・精密形状への対応力
真空注型は、複雑な形状や精密なディテールを持つ部品の製作にも高い対応力を発揮します。シリコーン型は柔軟性があるため、アンダーカットや複雑な内部構造を持つ形状でも、マスターモデルの細部まで忠実に転写し、一体成形することが可能です。
また、型から製品を取り出す際にも、シリコーン型の柔軟性が活かされ、複雑な形状でも型を傷つけることなく、製品を容易に取り出すことができます。これにより、デザインの自由度が高まり、製品設計の幅が大きく広がります。マスターモデルの精度が高ければ、非常に精密な部品も再現可能です。
真空注型のデメリット
真空注型は、試作や小ロット生産において非常に有効な製造方法ですが、特性上、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、真空注型が持つ主な課題や限界について詳しく解説します。
大量生産には不向き
真空注型で使用されるシリコーン型は、金属製の金型と比較して耐久性が低く、繰り返し使用による劣化が進みやすいという特性があります。
一般的に、一つのシリコーン型から製造できる製品数は数十個から数百個程度と限られており、それ以上の数を生産するには新たなシリコーン型を製作する必要があります。
このため、数千個、数万個といった大量生産を行う場合には、型製作のコストや時間、材料費の面で射出成形などの他の製造方法に比べて効率が悪く、不向きとされています。
寸法精度の限界
シリコーン型はゴムのような柔軟性を持つため、成形時にわずかな変形が生じることがあります。また、樹脂の収縮率も材料や形状によって異なるため、金属製の金型を使用する射出成形と比較すると、得られる製品の寸法精度には限界があります。
特に、非常に厳しい公差が求められる精密部品や、大型の製品では、この寸法のばらつきが課題となる場合があります。
表面仕上がりの課題
真空注型では、マスターモデルの表面状態がシリコーン型に転写され、それが製品の表面品質に直結します。
しかし、シリコーン型製作時の微細な気泡の混入や、型を繰り返し使用することによる劣化、あるいは型からの取り出し時の影響などにより、製品の表面に細かな痕跡や光沢のムラが生じることがあります。
特に、高い外観品質が求められる製品の場合、後加工(研磨、塗装など)による追加工程が必要となることがあり、これが全体のコストや納期に影響を与える可能性があります。
使用できる素材が限定される
使用できる素材が限定されることも真空注型のデメリットの一つとされます。
よくある質問
真空注型とはどのような型ですか?
真空注型は、特定の「型」そのものを指すのではなく、シリコーン製の型を用いて樹脂製品を成形する「製造方法」の一つです。マスターモデルから作られた柔軟なシリコーン型を真空環境下に置き、液体状の樹脂を注入・硬化させることで、マスターモデルの形状を忠実に再現した製品を製作します。主に試作品の製作や、数個から数百個程度の小ロット生産に活用されます。
真空注型のデメリットは何ですか?
真空注型の主なデメリットとしては、「大量生産には不向き」「寸法精度に限界がある」「表面仕上がりに課題がある」などが挙げられます。
射出成形とはどう違いますか?
真空注型と射出成形は、どちらも樹脂製品を成形する技術ですが、目的、使用する型、コスト、生産量、対応材料などに大きな違いがあります。
目的と生産量: 真空注型は主に試作や小ロット生産(数十個〜数百個)に適しているのに対し、射出成形は大量生産(数万個〜数百万個)を目的としています。
使用する型: 真空注型では、比較的安価で短期間に製作できるシリコーン型を使用します。一方、射出成形では、高価で製作期間が長い金属製の金型を使用します。
コストと納期: 真空注型は型製作コストが低く、短納期での製品提供が可能です。射出成形は金型製作に多大な初期投資と時間がかかりますが、一度型が完成すれば単価を抑えて高速に生産できます。
対応材料: 真空注型は主にウレタン樹脂やエポキシ樹脂などの液状樹脂が使われます。射出成形は熱可塑性樹脂全般に対応し、非常に多種多様な材料選択肢があります。
寸法精度: 射出成形は金属金型を使用するため、真空注型よりも高い寸法精度と安定した品質を実現できます。
まとめ
本記事では、真空注型がどのような技術であるか、その仕組みからメリット・デメリットまで解説しました。
プロテックジャパンでは、真空注型をはじめ、簡易ダイキャスト、射出成形、砂型鋳物にいたるまで、多彩な製造方法を提供しております。
お客様の「納期・コスト・必要送料・求める品質」といったご要望を丁寧にヒアリングし、最適な製造プランをご提案可能です。
他社では難しい小ロットのご希望にも低コストで対応できます。
まずはお気軽にご相談ください。
▼お問い合わせはこちら
https://www.protech-japan.jp/contact.html
▼当社が提供する真空注型はこちら
https://www.protech-japan.jp/products/resin/resin_cast.html