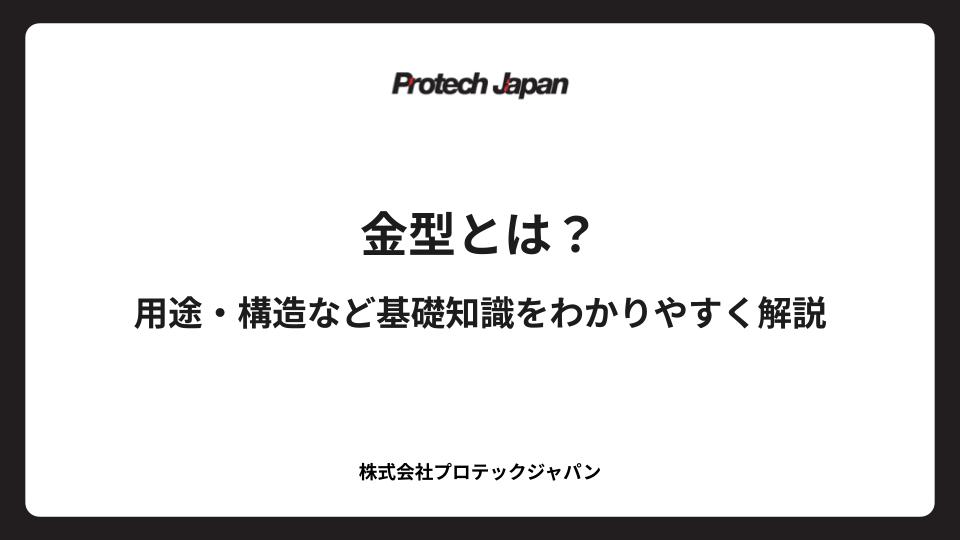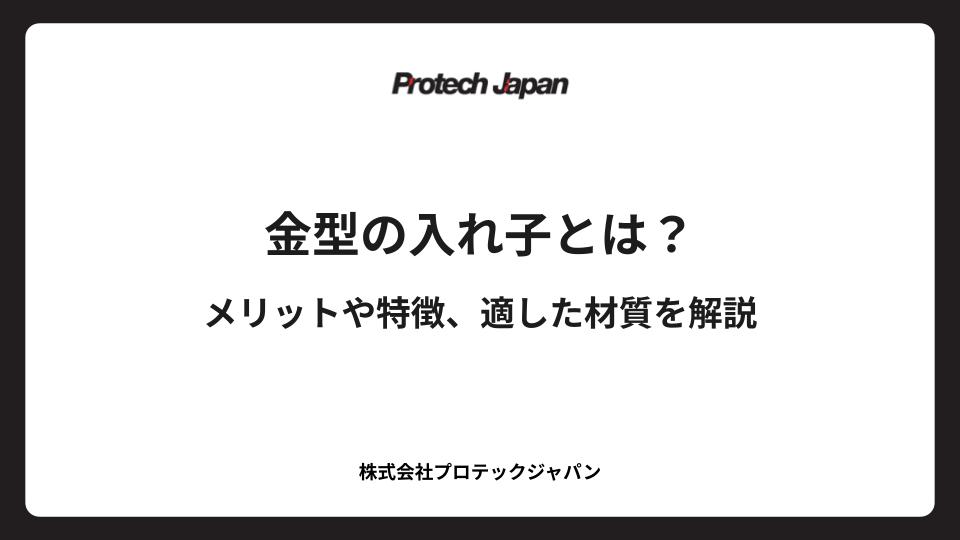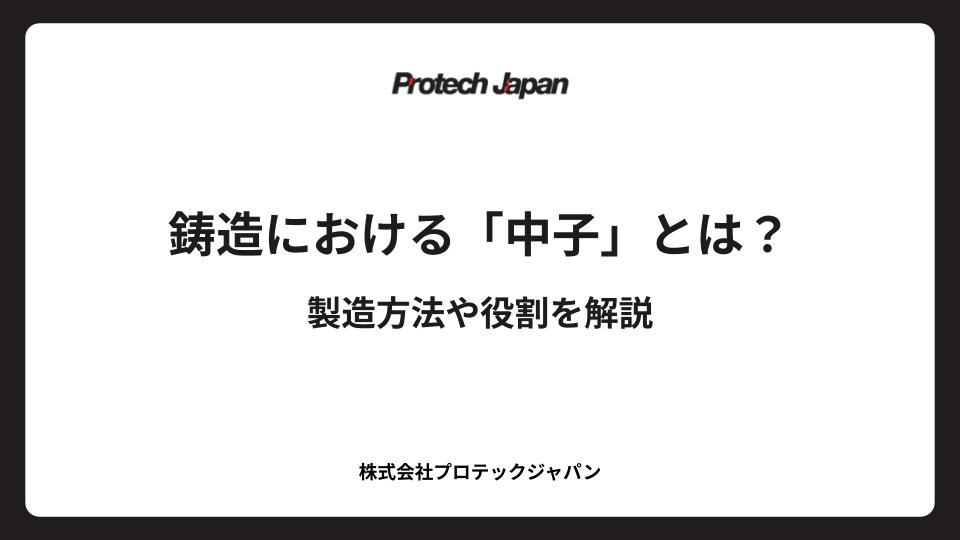この記事では、産業界で幅広く利用される砂鋳物の定義や製造工程、使用される材料、そして他の鋳造方法との違いまで解説します。
砂鋳物がなぜ現代のものづくりに不可欠なのか、その理由を理解することで、貴社の製品に適切な鋳造方法を選定する際の参考になれば幸いです。
砂鋳物とは何か
砂鋳物の定義
砂鋳物とは、砂を主成分とする鋳型(砂型)を用いて、溶解した金属を流し込み、冷却・凝固させることで目的の形状に成形する鋳造品、またはその製造方法全般を指します。
この鋳造方法は、紀元前から行われている最も歴史の長い鋳造技術の一つであり、その柔軟性とコスト効率の高さから、現代においても自動車部品、機械部品、建築部材など、幅広い産業分野で不可欠な製造技術として利用されています。
砂型鋳造法の基本原理
砂型鋳造法の基本原理は、まず製造したい製品の形状と同じ「原型(木型、金型、樹脂型など)」を用意することから始まります。この原型を鋳物砂の中に埋め込み、周囲を固めて鋳型(上型と下型)を形成します。
原型を取り除くと、その内部に製品の形状をした空洞(キャビティ)ができます。このキャビティに、溶解した金属(溶湯)を湯口から流し込み、冷却・凝固させます。金属が固まった後、砂型を壊して鋳物を取り出し、不要な部分(湯口、押湯など)を切断・研磨して最終製品が完成します。
砂型は基本的に一度の使用で壊されますが、使用済みの鋳物砂は多くの場合、回収・再生処理されて再利用されます。
他の鋳造方法の違い
砂型鋳造は、他の様々な鋳造方法と比較して、それぞれ異なる特性を持っています。
例えば、ダイカスト鋳造や金型鋳造(グラビティ鋳造、低圧鋳造など)は、金属製の金型を使用するため、高い寸法精度と滑らかな表面品質が得られ、特に大量生産に適しています。しかし、金型製作には高額な初期投資が必要となります。
一方、砂型鋳造は、比較的安価な砂型を使用するため、型製作コストを抑えることが可能です。このため、少量生産や大型部品、複雑な内部構造を持つ部品の製造に優れています。ただし、砂型特有の表面の粗さや、金型鋳造に比べて寸法精度に限界がある点が特徴です。
また、ロストワックス鋳造(精密鋳造)は、ワックス製の原型を用いることで非常に高い寸法精度と複雑な形状を実現できますが、工程が多段階でコストが高くなる傾向があります。
砂型鋳造は、これらの方法の中間に位置し、コスト、生産量、形状の複雑さ、要求される寸法精度など、様々な要素のバランスを考慮した上で、非常に汎用性の高い鋳造方法として広く採用されています。
砂鋳物の製造工程
砂鋳物の製造は、複数の精密な工程を経て行われます。ここでは、砂型鋳造法における具体的な製造プロセスを順を追って解説します。
鋳型製作
砂鋳物の品質を左右する最初の重要な工程が鋳型製作です。製品の形状を正確に再現するための型を、鋳物砂を用いて作ります。
模型の準備
鋳型を製作するために、まず製品の最終形状に収縮率などを考慮した「模型」を用意します。この模型は、木材、金属、樹脂などで作られ、一般的には「木型」や「金型」と呼ばれます。模型には、湯口(溶けた金属を流し込む部分)や押湯(凝固収縮を補う部分)などの鋳造方案も含まれます。
鋳物砂の調合と準備
鋳型を形成する鋳物砂は、単なる砂ではありません。主成分となる珪砂などの耐火性の砂に、粘土や有機物などの「結合剤」と水を混ぜ合わせ、適切な強度と通気性を持つように調合されます。これにより、鋳型が崩れにくく、かつ鋳造時のガスを逃がす特性が確保されます。
造型作業
準備された鋳物砂を用いて、模型の形状を転写する作業を「造型」と呼びます。一般的には、模型を上下に分割し、それぞれ「上型(上半分)」と「下型(下半分)」を造型します。砂を突き固めることで、模型の形状が砂型に正確に転写されます。
型締めと中子の設置
造型された上型と下型を正確に合わせる作業を「型締め」と呼びます。この際、製品内部に空洞や特定の形状が必要な場合は、事前に製作しておいた「中子(なかご)」を型内に設置します。中子も鋳物砂で作られることが多く、高温の溶湯に耐える強度と、鋳造後に容易に除去できる特性が求められます。
溶解と注湯
鋳型が完成したら、いよいよ金属を溶かし、型に流し込む工程に移ります。
金属の溶解と成分調整
鋳造に使用する金属(鉄、アルミニウム、銅合金など)を、電気炉やキュポラなどの溶解炉で溶かします。この際、目標とする材質の特性を得るために、合金成分の調整や不純物の除去が行われます。溶湯の温度管理も非常に重要であり、適切な注湯温度を保つことで、鋳造欠陥を防ぎます。
注湯作業
溶解され、適切な温度に調整された溶湯を、完成した鋳型の湯口から流し込みます。溶湯が鋳型内部のキャビティ(空洞)に均一に充填されるように、ゆっくりと、しかし途切れることなく注ぎます。この工程は、鋳物の品質に直結するため、細心の注意を払って行われます。
凝固と冷却
鋳型に注ぎ込まれた溶湯は、時間の経過とともに冷却され、液体から固体へと変化します。この「凝固」の過程で、金属は収縮し、最終的な製品形状が形成されます。鋳型内で十分な時間をかけて冷却させることで、内部応力の発生を抑え、健全な組織を得ることができます。
型ばらしと製品取り出し
溶湯が完全に凝固し、十分冷却されたら、鋳型を分解して鋳物製品を取り出す「型ばらし」を行います。砂型は一度使用すると壊れてしまうため、製品を取り出す際に型を壊す必要があります。この工程で、製品に付着した余分な砂を取り除きます。
仕上げ工程
鋳型から取り出された鋳物製品は、まだ最終的な製品ではありません。いくつかの仕上げ工程を経て、出荷可能な状態になります。
ばり取りと砂落とし
型ばらし後、製品には湯口や押湯、パーティングライン(型の合わせ目)に沿って「ばり(余分な金属)」が付着しています。これらをグラインダーやチゼルなどを用いて除去する作業を「ばり取り」と呼びます。また、製品表面や内部に残った鋳物砂を完全に除去する「砂落とし」も行われます。
ショットブラスト
製品表面に残った砂や酸化皮膜を除去し、表面を均一にきれいにしたり、表面硬度を高めたりするために、「ショットブラスト」と呼ばれる処理が行われることがあります。これは、小さな金属粒(ショット)を製品に高速で衝突させることで、表面を研磨する技術です。
砂鋳物に使用される材料
鋳物砂の種類と特性
鋳物砂は、鋳型を形成するための基材となる砂であり、その種類によって耐熱性、熱膨張率、粒度分布などが異なります。鋳物の材質や形状、要求される精度に応じて最適な砂が選ばれます。
珪砂(けいさ)
最も一般的に使用される鋳物砂です。主成分は二酸化ケイ素(SiO2)で、安価で入手しやすいため、幅広い鋳物製造に利用されます。耐熱性は比較的高いものの、特定の温度域で結晶構造が変化し熱膨張を起こす特性があります。
ジルコン砂
ジルコン(ZrSiO4)を主成分とする砂で、珪砂に比べて非常に高い耐熱性と低い熱膨張率を持つのが特徴です。そのため、寸法精度が求められる鋳物や、高温での鋳造が必要な特殊鋼鋳物などに使用されます。高価であるため、必要に応じて部分的に使用されることもあります。
クロマイト砂
クロマイト(FeCr2O4)を主成分とする砂で、熱伝導率が高く、鋳物の冷却速度を速める効果があります。特にマンガン鋼などの粘性の高い合金の鋳造において、鋳物と鋳型の反応を抑制し、表面欠陥を防ぐために用いられます。
セラミック砂
人工的に製造される球状の砂で、非常に均一な粒度分布と高い耐熱性、低い熱膨張率を特徴とします。優れた流動性により鋳型充填性が良く、鋳物の表面粗さや寸法精度を向上させることができます。高機能鋳物や精密鋳造で利用されます。
結合剤の種類
結合剤は、鋳物砂の粒子同士を結合させ、鋳型の強度を保つために不可欠な材料です。鋳造方法や要求される鋳型の特性によって、様々な種類の結合剤が使い分けられます。
粘土系結合剤
主にベントナイトが使用されます。水と混合することで粘性を持ち、砂粒子を結合させます。生型鋳造法において広く用いられ、通気性が良く、鋳型を繰り返し使用できるリサイクル性に優れています。鋳型は比較的柔らかく、鋳造後に崩壊しやすい性質があります。
水ガラス系結合剤
ケイ酸ナトリウム(水ガラス)を主成分とし、二酸化炭素(CO2)ガスを吹き込むことで硬化する特性を持ちます(CO2ガス型)。硬化速度が速く、鋳型の寸法安定性に優れますが、鋳型が崩壊しにくいため、鋳物を取り出す際に作業負荷がかかることがあります。
レジン系(有機系)結合剤
合成樹脂を主成分とする結合剤で、熱や触媒反応によって硬化します。 代表的なものにフェノール樹脂やフラン樹脂があり、これらはシェルモールド法や自硬性鋳型法で用いられます。高強度で寸法精度の高い鋳型が得られ、鋳物の表面品質向上に寄与します。ただし、鋳造時に有機成分が分解されるため、ガス発生や臭気の問題が生じることがあります。
セメント系結合剤
ポルトランドセメントなどを結合剤として使用し、水と混合して硬化させます。主に大型の鋳物や、少量の生産で鋳型を再利用しない場合に用いられます。硬化に時間がかかりますが、非常に強固な鋳型を形成できます。
砂鋳物のメリット
複雑形状への対応力
砂型鋳造法は、その特性上、非常に複雑な形状の鋳物を製造できる点が大きなメリットです。砂は流動性に富み、型に充填しやすいため、内部に空洞を持つ部品や、アンダーカットのある複雑な外形を持つ部品も一体成形が可能です。これにより、複数の部品を溶接や機械加工で結合する必要がなくなり、製造工程の簡素化、コスト削減、および製品の信頼性向上が期待できます。
コストと効率性
砂型鋳造に使用される鋳型は、比較的安価な鋳物砂と結合剤を主成分とするため、金型(永久型)に比べて型製作の初期費用を大幅に抑えることができます。特に少量生産や試作品の製造において、金型を製作するコストや時間をかけずに、迅速かつ経済的に部品を供給することが可能です。
表面の粗さと精度
砂型鋳物特有の表面の粗さは、特定の用途においてメリットとなる場合があります。例えば、塗装やコーティング、接着剤の密着性を向上させるための下地として機能することがあります。また、摩擦係数を調整したい場合など、意図的に粗い表面が必要とされる製品にも適しています。
砂鋳物のデメリット
寸法精度の限界
砂鋳物は、砂型という比較的柔軟な型を使用するため、他の鋳造方法に比べて寸法精度に限界があります。
鋳造時の熱による砂型の膨張・収縮、あるいは型ばらしの際の変形などにより、製品の寸法にばらつきが生じやすくなります。特に高い寸法精度が求められる部品や、厳密な公差が設定されている部品には、砂鋳物単体での対応が難しい場合があります。
環境負荷の問題
鋳造に使用された鋳物砂は、繰り返し使用できるものの、劣化や異物の混入により最終的には廃棄物となります。
大量に発生する使用済み鋳物砂の適切な処理やリサイクルは、環境負荷を低減するための重要な課題です。また、有機結合剤を用いた鋳造法の場合、鋳造時の高温により結合剤が分解され、VOC(揮発性有機化合物)や悪臭ガスが発生することがあります。これらのガスは作業環境の悪化だけでなく、大気汚染の原因となる可能性もあるため、排ガス処理設備や適切な換気対策が求められます。
さらに、砂の取り扱い工程では粉塵が発生しやすく、作業者の健康保護や周辺環境への影響を考慮した集塵対策も不可欠です。
まとめ
砂鋳物は、その柔軟性とコスト効率の高さから、現代の製造業において不可欠な鋳造方法です。
プロテックジャパンは、砂鋳物はもちろん、ダイキャスト、ロストワックスなど、お客様の製品に最適な鋳造方法をワンストップで提案します。複雑な部品の設計から、試作、量産、そして仕上げまで、一貫したサポート体制でお客様のものづくりを成功へと導きます。
「どの鋳造方法が最適かわからない…」
「コストを抑えて複雑な部品を作りたい」
など、ものづくりに関するお悩みは、プロテックジャパンにお任せください。長年の経験と確かな技術力で、お客様の課題解決に貢献します。お気軽にご相談ください。
▼お問い合わせはこちら
https://www.protech-japan.jp/contact.html
▼当社が提供する砂鋳物はこちら